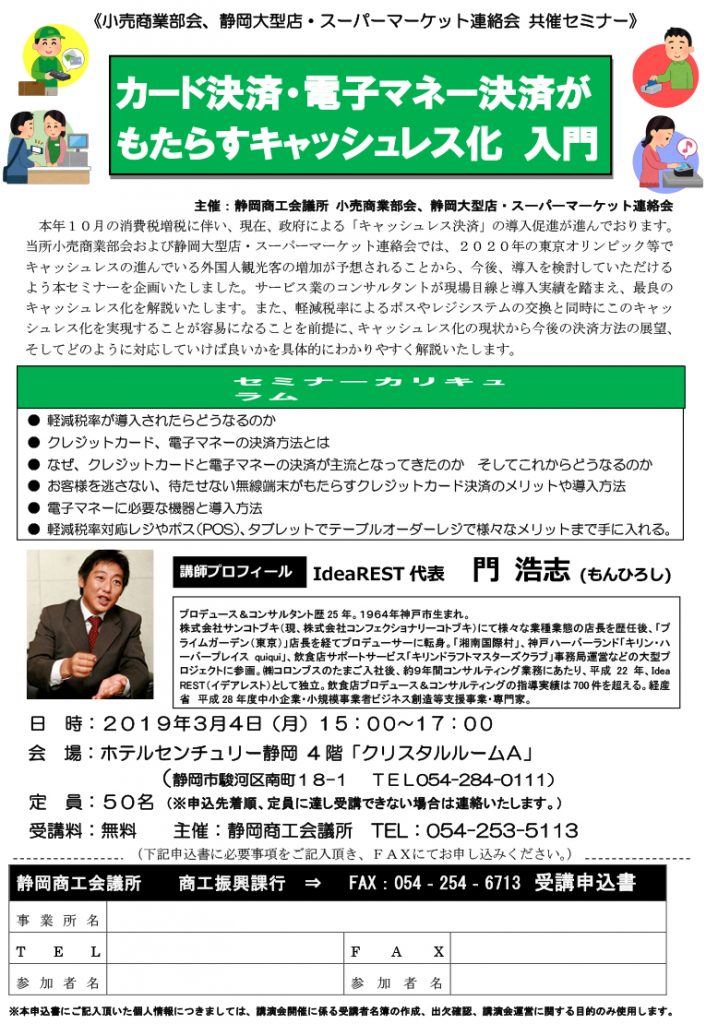“`html
2030年問題に備える飲食店経営とメニュー開発・人材確保の戦略
日本の外食市場は、これまで「人口増加」「若い労働力」「低コスト人件費」を前提に発展してきました。しかし、2030年に向けて状況は大きく変わります。高齢者比率は上昇し、労働生産人口は大幅に減少。それに伴い、飲食店 経営・飲食店 メニュー開発・飲食店 人材確保のすべてを見直さなければ生き残れない時代に入っています。 本記事では、「2030年問題」が飲食店経営に与える影響を整理したうえで、ロイヤルリピート客の育成、メニュー開発の再設計、人材確保・外国人雇用・DXの活用まで、実践的な対策を1〜10章に分けて解説します。
目次
1. 2030年問題と飲食店経営
「2030年問題」とは、2030年前後に高齢者が人口の約3分の1を占め、労働生産人口が大きく減少すると予測されている社会構造の変化を指します。 この変化は、飲食店 経営にも直接的な影響を与えます。具体的には、
- 外食に回せるお金・時間・体力を持つ人の構成が変わる
- 働き手(キッチン・ホール・店長候補)の絶対数が減る
- 人件費や社会保険料など、固定費がじわじわと増加する
つまり、「客数が減る」「スタッフが集まらない」「コストは上がる」という三重苦に直面する可能性が高いのです。 この状況で、従来どおりの考え方・運営方法のままでは、売上が横ばいでも利益が減り続けるという事態に陥ります。今、飲食店 経営者が考えるべきなのは、
- 限られた市場・限られた顧客の中で、どう選ばれ続けるか
- 限られた人員で、どう高い生産性を実現するか
- どのように「負担の少ない働き方」と「適正な利益」を両立させるか
という視点です。そのためには、次章で説明する4つのリスクを正しく理解しておく必要があります。
2. 2030年問題が飲食店にもたらす4つのリスク
2-1. 新規顧客獲得競争の激化
人口が減少し、外食市場のパイが縮小する中で、新規顧客はどの業態にとっても「取り合い」の状態になります。
- 近隣店舗との価格・内容・雰囲気の比較
- デリバリー・テイクアウト・中食との競合
- フードコートや商業施設内の他テナントとの比較
これまで「駅前だから」「人通りが多いから」という理由である程度の集客ができていた立地であっても、選び方が変われば簡単に沈みます。つまり、「ただそこにあるだけ」では選ばれない時代が来ています。
2-2. 最低賃金上昇と人材確保競争
最低賃金は毎年のように引き上げられています。これに対して、売価をそのまま据え置いていては、当然ながら利益は圧迫されます。 さらに、労働人口の減少によって、
- 大企業やチェーン店が高時給・厚待遇で人材を囲い込む
- 中小飲食店は、同じ条件では太刀打ちできない
という構図が一層強くなります。「時給を上げれば人が来る」時代はすでに終わりつつあると考えた方がよいでしょう。
2-3. 「3Kイメージ」と調理人不足
飲食業は長い間、「3K」=きつい・汚い・危険な仕事と見なされてきました。そこに、調理人は「長時間労働」「修行が必要」というイメージが加わり、若い人材が敬遠しがちです。 その結果、
- 本格的な料理が作れる人材が減る
- メニュー開発を担える人材も育ちにくくなる
- 既製品や冷凍食品への依存度が高まり、差別化が難しくなる
といったリスクが発生します。これは、単に「人が足りない」問題を超えて、飲食店 メニュー開発力そのものが細っていく危険を意味します。
2-4. 離職率上昇と定着率の低下
人材確保が難しくなる中で、優秀な人ほど条件の良い会社へ流れていく傾向が強まります。
- 給料・賞与・福利厚生の差
- 労働時間・休日数の差
- マネジメントスタイルや人間関係の問題
これらが積み重なると、
- 採用してもすぐに辞めてしまう
- 中堅層が育たず、いつまでもオーナーや店長に負担が集中する
といった悪循環が起こります。2030年問題に備えるには、「どう採るか」だけでなく「どう続けてもらうか」まで含めた人材戦略が必要です。
3. これからの飲食店経営に必要な視点
ここまで見てきたように、2030年問題は「売上を増やす」「コストを下げる」といった単純な話ではありません。飲食店 経営そのものの前提が変わると考えるべきです。 これからの飲食店に必要な視点は、次の3つの柱に整理できます。
- 顧客戦略:ロイヤルリピート客を増やす仕組み
- 商品戦略:メニュー開発と収益構造の再設計
- 人と仕組みの戦略:人材確保・定着・DX(デジタル化)
言い換えると、
- 「誰に来てもらうか」=ターゲットとファン化
- 「何を売るか」=飲食店 メニュー開発とブランド設計
- 「誰と・どう回すか」=飲食店 人材確保とオペレーション設計
の3つを同時に設計し直す必要があります。
3-1. 「現場で頑張る」から「仕組みで回す」へ
これまでの飲食店は、「社長や店長、料理長がとにかく現場で頑張る」ことで成り立ってきたケースが多くありました。
- 社長自らが現場に入り、皿洗い・ホール・仕込みまでこなす
- 料理長が朝から深夜まで15時間労働が当たり前
- 店長がシフト調整・発注・クレーム対応・アルバイト教育を一手に抱え込む
こうした“気合と根性”の経営は、人が豊富にいた時代だからこそギリギリ成り立っていたスタイルです。しかし、
- 人が採れない
- 採れても長く続かない
- オーナー自身も年齢を重ねていく
という現実を考えると、「誰か一人が身を削って支える」やり方には限界があります。これからは、人に依存する経営から、仕組みに支えられる経営への転換が必須です。 そのための具体的な手段が、次章以降で解説する「ロイヤルリピート客の育成」「メニュー開発の再設計」「人材確保・外国人雇用・DXの活用」です。
4. ロイヤルリピート客を増やす会員化・ファン化戦略
4-1. ロイヤルリピート客の定義と価値
新規顧客の獲得には、広告費、SNS運用、ポータルサイトの手数料など、年々コストがかかるようになっています。その一方で、ロイヤルリピート客は「宣伝費ゼロで売上を運んでくれる存在」です。 ここではロイヤルリピート客を、
店舗やブランドへの愛着・信頼が深く、頻繁に利用するだけでなく、口コミやSNSで紹介してくれるなど、売上と新規客の両方に貢献してくれるお客様
と定義します。 人口減少・競争激化の時代には、1人のロイヤルリピート客の価値は、以前よりも何倍にも膨らむと考えるべきです。新規客を追い続けるだけではなく、「今来てくれているお客様をいかにロイヤル化するか」が飲食店 経営の重要なテーマになります。
4-2. 割引ではなく「特別感」でファン化する
多くの飲食店は、会員施策と聞くと、
- ポイントカード
- 割引クーポン
- ドリンク1杯無料
といった「値引き」を思い浮かべます。しかし、値引きにだけ反応するお客様は、より安い店が現れた瞬間にそちらへ流れてしまいます。 2030年問題に備える飲食店 経営では、価格ではなく「特別感」でファン化する発想が重要です。 例えば、次のような取り組みが考えられます。
- 会員だけが注文できる裏メニュー
- 会員ランクによって予約できる裏コース(おまかせコース)
- 会員限定のプレミアムドリンクやペアリング体験
- 新作メニューの先行試食会への招待
重要なのは、「自分はこの店の会員だからこそ得られる特別な体験がある」と感じてもらうことです。「割引されるから来る店」ではなく「好きだから来る店」を目指すことが、ロイヤルリピート客の育成には欠かせません。
4-3. マイレージ型会員システムの設計ポイント
航空会社のマイレージプログラムのように、飲食店でも「ステータス制」を導入することができます。 例えば、以下のようなイメージです。
- レギュラー:会員登録した全員
- シルバー:年間来店5回以上、または年間利用額5万円以上
- ゴールド:年間来店12回以上、または年間利用額12万円以上
- プラチナ:年間来店24回以上、または年間利用額25万円以上
それぞれのステータスごとに、
- ウェルカムドリンクサービス(割引ではなく「特別な一杯」を用意)
- マスター(店主)おすすめの一皿サービス
- イベントや貸切会の優先案内
- カウンターや窓際など特等席の優先予約枠
などの特典を用意すると、「あと1回来店すればシルバーに上がる」「誕生日はここで過ごそう」という前向きな動機づけができます。 これらをLINE公式アカウントや会員アプリ、顧客管理システムと連動させれば、DX時代に適した飲食店 経営の基盤が整います。
5. 2030年を見据えた「飲食店 メニュー開発」の新常識
5-1. 原価率だけでなく「オペレーション原価」を見る
従来の飲食店 メニュー開発では、「原価率○%以内に抑える」という考え方が主流でした。しかし、2030年問題を踏まえると、原価率の計算だけでは不十分です。 今後のメニュー開発で考えるべき「コスト」は、次のようなものを含んだ総合的なオペレーション原価です。
- 仕込みにかかる時間と人件費
- 調理工程の複雑さ(何ステップ必要か)
- 必要なスキルレベル(ベテランでなければ作れないのか)
- 廃棄ロスが出やすい食材かどうか
- 盛り付けの手間・皿数の多さ
例えば、
- 原価率25%だが、仕込みも調理も非常に手間がかかるメニュー
- 原価率30%でも、セントラルキッチンでまとめて仕込み、店舗では簡単な仕上げだけのメニュー
この2つを比べたとき、最終的な利益が大きいのは後者であるケースも多くなります。「原価率」ではなく「時間と人件費を含めた総合採算」でメニューを評価することが重要です。
5-2. 二毛作・三毛作メニューで生産性を上げる
2030年問題への対策として、メニュー開発段階から「二毛作・三毛作」を前提に考えることは非常に有効です。 例えば、ローストビーフを仕込む場合を考えてみましょう。
- ランチ:ローストビーフ丼、ローストビーフプレート
- ディナー:ローストビーフのカルパッチョ、サラダ、メインディッシュ
- テイクアウト:ローストビーフ弁当、ローストビーフサンド
このように、1つのベース仕込みを複数商品に展開すれば、
- 仕込みの手間は1回で済む
- ロスが減り、利益率が改善する
- スタッフ教育も「仕込み+展開パターン」を教えるだけで済む
というメリットが生まれます。「仕込みを増やす」のではなく「仕込みの活かし方を増やす」という発想が、これからの飲食店 メニュー開発には欠かせません。
5-3. セントラルキッチンとIot機器で味を標準化する
複数店舗展開をしている、あるいは今後検討している飲食店にとって、セントラルキッチン+Iot機器の活用は強力な武器になります。 基本的な流れの一例は次の通りです。
- ベテラン料理人をセントラルキッチンに集約する
- ソース、スープ、ベース食材などの仕込み・2次加工を集中して行う
- ブラストチラー・ショックフリーザーで急速冷却・冷凍する
- 各店舗に冷蔵・冷凍状態で配送する
- 店舗ではスチコンなどのIot機器に登録したプログラムで仕上げる
これにより、
- 各店の「料理人依存」から脱却できる
- 味のバラつきが減り、ブランドイメージが安定する
- 外国人スタッフや未経験スタッフでも再現性の高い調理が可能になる
国や自治体の補助金(IT導入補助金・設備投資補助金など)を活用すれば、初期費用の負担も軽減できます。単なる設備投資ではなく、「人材不足対策」「メニュー開発の仕組み化」と一体となった投資として考えることが大切です。
6. 「飲食店 人材確保」戦略の再構築と外国人雇用の活用
6-1. 低価格ビジネスモデルからの卒業
人材確保に悩む多くの飲食店の共通点は、いまだに「低価格・高回転・薄利多売」モデルから抜け出せていないことです。 このモデルでは、
- 単価が低いため、多くの客数をさばかなければ利益が出ない
- 忙しさのわりに利益が残らず、人件費に十分なお金を回せない
- 人件費を抑えるために少人数で回し、さらに現場が疲弊する
という悪循環に陥ります。2030年に近づくほど、このモデルは「人がいないのに忙しい」「忙しいのに儲からない」という最悪の状態になりかねません。 だからこそ、飲食店 経営のビジネスモデルそのものを「適正価格・適正利益」へと転換する発想が必要です。
- 原価と人件費を踏まえたメニュー価格の見直し
- コンセプトや体験価値を強化して、値上げの理由をしっかり伝える
- 値段だけでなく「ストーリー」や「こだわり」で選ばれる店を目指す
この転換なしに、飲食店 人材確保に本気でお金と時間を使うことは難しいでしょう。
6-2. 採用ターゲットの多様化
これからの飲食店 人材確保では、「若いフルタイムスタッフだけ」を想定した採用は限界です。採用ターゲットを多様化し、それぞれに合った働き方を用意することが重要です。
- 若手スタッフ(20〜30代) キャリアアップやスキル習得を重視し、店長・料理長・独立などのストーリーを描ける環境を用意する。
- 主婦・主夫層 子育てや家事との両立を前提に、「短時間」「曜日固定」「時間帯固定」のシフトを用意し、ランチタイム要員として活用する。
- シニア・第二のキャリア層 体力的にフルタイムは難しくても、仕込み・洗い場・開店準備などで経験を活かしてもらう。
- 外国人スタッフ 接客・調理の両方で活躍でき、インバウンド対応や多言語コミュニケーションという強みも持つ。
この中でも特に、外国人雇用は2030年以降の飲食店 人材確保において非常に重要な要素になります。
6-3. 外国人雇用を戦略的に活用する
外国人スタッフの雇用は、「人手不足を埋めるための最後の手段」ではなく、戦略的な選択肢として考えるべきです。適切に活用できれば、飲食店 経営に多くのメリットをもたらします。
(1)在留資格(ビザ)の理解と合法的な雇用
まず重要なのは、在留資格(ビザ)の種類と条件を正しく理解することです。
- 留学生(資格外活動許可):週28時間までなど、勤務時間に制限がある
- 特定技能(外食業など):フルタイム勤務が可能で、一定の技能・日本語能力が求められる
- 技術・人文知識・国際業務:主に企画・管理・翻訳・通訳などの職種
どのビザであればどのような業務ができるのか、週何時間まで働けるのかを事前に確認し、法律に沿った雇用管理を徹底することが大前提です。
(2)言語サポートとマニュアル整備
日本語が流暢でない外国人スタッフを採用する場合は、「言葉に頼りすぎない教育設計」が大切です。
- 写真やイラストを多用した作業マニュアル
- 手順を動画でまとめた研修コンテンツ
- よく使う日本語フレーズ集(接客用・厨房用)
などを用意することで、言葉の壁を越えて業務を覚えてもらうことができます。
(3)文化・宗教への配慮
外国人雇用では、文化や宗教への配慮も重要なポイントです。例えば、
- イスラム教徒スタッフがいる場合、豚肉やアルコールの扱い方・まかない内容に配慮が必要
- 宗教上の理由で特定の曜日や時間帯に礼拝が必要な場合、その時間をシフトに反映する
こうした配慮は、スタッフにとって「自分を尊重してくれている職場」と感じてもらえる重要な要素です。同時に、インバウンド客や多様なバックグラウンドを持つお客様に対しても、信頼感を伝えることにつながります。
(4)外国人スタッフの強みを活かす
外国人スタッフは、単に「人手が増える」だけでなく、飲食店 メニュー開発やマーケティングにも貢献できます。
- 本場の味・食文化の知識をメニューに反映する
- 母国語・英語での接客で、インバウンド客の満足度を高める
- 海外向けSNS発信や口コミサイトへの情報発信をサポートしてもらう
このように、外国人スタッフを「お店の価値を高めるパートナー」として位置づけることで、2030年問題を乗り越える大きな力となります。 
6-4. 教育・評価・キャリアパスで「辞めたくない職場」をつくる
採用がうまくいっても、すぐに辞めてしまっては意味がありません。「ここで働き続けたい」と思ってもらう職場環境をつくることが、飲食店 人材確保の本質です。 そのためには、次の3つが重要です。
- 教育:何をいつまでに覚えればいいかを明確にする
- 評価:できるようになったことをきちんと評価する
- キャリアパス:半年後・1年後・3年後の成長イメージを描けるようにする
例えば、
- 入社1ヶ月でできるようになってほしい業務リスト
- 3ヶ月後・半年後の目標スキル
- ホールリーダー・キッチンリーダー・店長候補へのステップ
などをあらかじめ提示し、1つできるようになったら時給アップや役職手当で目に見える形で評価することが大切です。 日本人・外国人を問わず、「ここで働けば成長できる」「自分の居場所がある」と感じられる職場は、定着率が高く、採用面でも口コミで有利になります。
7. DX・業務効率化で人手不足時代を乗り切る
人材不足の時代において、DX(デジタルトランスフォーメーション)と業務効率化は欠かせません。ただし、「人件費を削るためだけ」のDXは失敗しやすく、「人が人らしい仕事に集中できるようにするDX」を目指すことが重要です。
7-1. セルフオーダーは「人を減らす」ためだけに使わない
タブレット注文やQRコードオーダーなどのセルフオーダーシステムは、飲食店DXの代表例です。 メリットとしては、
- 注文ミスの減少
- オーダー処理のスピードアップ
- 注文データの蓄積による分析(よく出るメニュー、時間帯別の傾向など)
一方で、デメリットも存在します。
- スタッフからのおすすめやペアリング提案が減る
- お客様との会話が減り、ニーズや不満に気づきにくくなる
- 年配のお客様には操作がわかりにくく、ストレスになることもある
そのため、セルフオーダーは「ホールスタッフの仕事を奪う道具」ではなく、「ホールスタッフが人にしかできない仕事に集中するための道具」として位置づけるべきです。 例えば、
- オーダー・会計はセルフ化して効率化
- ウェルカム・料理説明・追加提案・お見送りなどはスタッフが担当
というハイブリッド型運用を目指すことで、DXとホスピタリティを両立した飲食店 経営が可能になります。
7-2. Iot機器・セントラルキッチンの本当の価値
スチームコンベクションオーブン、ブラストチラー、ショックフリーザーといったIot対応機器は、単なる「便利な調理器具」ではありません。
- 温度・時間・スチーム量などをプログラムとして登録できる
- 誰が操作しても同じ品質に近い仕上がりが再現できる
- セントラルキッチンとの連携で、仕込みと仕上げを分業できる
これらを活用することで、
- ベテランの勘や経験を「データ」として残せる
- 新人や外国人スタッフでも短期間で戦力化できる
- 人材不足の時代でも、安定した品質の料理を提供できる
という、「人材不足に強いキッチン体制」を構築することができます。 
8. 3Kイメージを脱却する職場環境づくり
飲食店 人材確保を語るうえで、「3Kイメージ」の払拭は避けて通れません。どれだけ魅力的なメニューを開発しても、どれだけDXを進めても、「働きたくない職場」では人は集まりません。
8-1. 労働時間・休憩・シフトの改善は最優先課題
まず取り組むべきは、長時間労働の是正と休憩時間の確保です。
- 開店前の仕込みをセントラルキッチンや外部委託に移す
- 閉店後の片付け・清掃の一部を外部業者に任せる
- ランチとディナーの間にしっかりとした休憩時間を設ける
などの工夫により、1人あたりの負担を減らすことができます。これは、日本人スタッフだけでなく、外国人スタッフにも大きく影響します。「無理なく働ける職場」であることが、定着率向上と採用力アップにつながります。
8-2. 清潔感と安全性への投資が「採用力」を左右する
「汚い・危険」と感じる職場では、どれだけ時給を上げても人は定着しません。
- 厨房床に滑りにくいマットを敷く
- 排煙・換気を改善し、熱気や煙を軽減する
- ゴミ置き場・バックヤードを整理整頓する
- 更衣室やロッカーを整備し、スタッフに「自分のスペース」を持ってもらう
こうした投資は、従業員満足度を上げるだけでなく、求人広告や採用ページに写真として掲載することで、採用力アップにも直結します。
8-3. クレーム対応マニュアルとメンタルケア
クレーム対応は、スタッフの心理的負担が大きい業務のひとつです。特に、経験の浅いスタッフや外国人スタッフにとっては、大きなストレス要因になりえます。 そのためには、
- クレーム発生時の対応フローをマニュアル化する
- スタッフ一人で抱え込まず、必ず上長が出るルールを作る
- クレーム後に、対応したスタッフに感謝とフォローの声をかける
といった仕組みが必要です。「クレームが怖いから辞める」という事態を防ぎ、安心して働ける職場づくりにつながります。
9. 今すぐ取り組みたい7つのアクションチェックリスト
ここまでの内容を踏まえ、今すぐに着手できるアクションを7つに整理しました。すべてを一度にやる必要はありませんが、「まず1〜2個決めて始める」ことで、2030年問題への備えが現実的になります。
- 顧客データを整理する レジデータ・予約台帳・SNSフォロワーなどから、常連客・ロイヤルリピート候補を把握する。
- 会員化・ファン化の設計を始める 会員ランク・特典・来店動機を整理し、まずは簡易版の会員制度からスタートしてみる。
- メニューを「儲かる/儲からない」で棚卸しする 原価率だけでなく、仕込み時間・手間・ロスを含めたオペレーション原価で評価し直す。
- 二毛作・三毛作メニューのアイデアを出す 既存の人気メニューから、「ランチ」「ディナー」「テイクアウト」への展開案を3つ以上考える。
- 設備投資と補助金情報を確認する スチコン・ブラストチラー・ショックフリーザーなど、Iot機器導入の可能性と補助金の有無を調べる。
- 求人内容・採用ターゲットを見直す 若手・主婦・シニア・外国人、それぞれに響くメッセージや条件を整理し、求人票を作り直す。
- 現場スタッフと「働きやすさ改善会議」を開く 週1回15分でもよいので、「不満」「困りごと」「改善アイデア」を共有する場をつくる。
10. まとめ|2030年問題は「淘汰」と「チャンス」の両方
2030年問題は、飲食店 経営にとって確かに大きなリスクです。人口減少・人手不足・コスト増という厳しい条件の中で、これまでと同じやり方を続けていては、ジリジリと体力を削られてしまいます。 しかし同時に、それは中途半端な店が淘汰され、本気で価値を提供する店だけが残る時代になるということでもあります。
- ロイヤルリピート客を増やす「顧客戦略」
- 飲食店 メニュー開発とセントラルキッチン活用による「商品戦略」
- 飲食店 人材確保・外国人雇用・DX活用を組み合わせた「人と仕組みの戦略」
この3つを今から少しずつ進めていけば、2030年以降も「選ばれ続ける飲食店」として生き残ることは十分可能です。 未来は、勝手に良くも悪くもなりません。今の一歩が、2030年の姿を決めると言っても過言ではありません。今日からできる小さなアクションから、ぜひ始めてみてください。 監修:イデアレスト(飲食店経営コンサルティング・開業・メニュー開発) 飲食業界専門の開業支援・事業再構築・収益改善をサポート。
筆者情報・信頼性の根拠
 IdeaREST 代表 門 浩司 / Hiroshi Mon
IdeaREST 代表 門 浩司 / Hiroshi Mon
プロデューサー & コンサルタント歴 32年
1964年兵庫県神戸市生まれ
㈱サンコトブキにて 様々な業種業態の店長を歴任後、 「プライムガーデン (東京)」店長を経て プロデューサーに転身。「 湘南国際村 」、 神戸ハーバーランド 「キリン ・ ハーバープレイス quiqui 」、 飲食店 サポート サービス 「 キリン ドラフトマスターズ クラブ」 事務局運営 などの大型プロジェクトに参画。 ㈱コロンブスのたまご入社後、 9年間 コンサルティング業務にあたり、 平成22年、 Idea REST( イデアレスト )として独立。 飲食店プロデュース & コンサルティングの指導実績は700件を超える。
●学校法人 服部栄養専門学校 服部学園 非常勤講師
●公益財団法人石川県、和歌山県、鹿児島県、岡山県、沖縄県 専門家
●スマートエキスパート 専門家
●商工会議所 エキスパート派遣事業 専門家
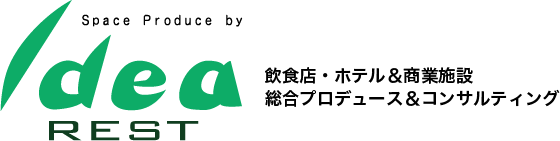
 IdeaREST 代表 門 浩司 / Hiroshi Mon
IdeaREST 代表 門 浩司 / Hiroshi Mon